日本において「賃貸か持ち家か」という議論は、長らく人々の関心を集めてきました。「一国一城の主」という言葉に象徴されるように、持ち家を持つことは安定や成功の証とされてきました。しかし、近年は社会や経済の変化、ライフスタイルの多様化により、この伝統的な価値観が揺らいでいます。住宅を購入するか賃貸で暮らすかという選択は、単なる好みの問題ではなく、将来の生活設計や資産形成に直結する重大な意思決定です。
私自体は賃貸派なので持ち家よりも賃貸を支持しています。そこでこの議題について①経済的観点、②移動のしやすさ、③新築プレミアム、④日本の人口減少と住宅需要、⑤地方と都市の違い、さらに⑥文化的・心理的要素を含めて比較し私が賃貸派になった理由を述べようと思います。
経済的観点
住宅購入は「資産になるから有利」と語られることがあります。しかし、実際の数字で比較すると、必ずしもそうとは言えません。
例えば、4,000万円の新築マンションを35年ローンで購入すると仮定します。変動金利0.6%であれば総返済額は約4,400万円程度ですが、金利上昇局面に入れば総額は5,000万円を超えることもあります。さらに固定資産税や火災保険、マンションであれば管理費や修繕積立金が毎月発生し、築年数が経過するにつれてこれらの負担は増えていきます。
一方、賃貸は家賃が永続的に発生するものの、ライフステージに合わせて住居費を調整できる柔軟性があります。余剰資金を投資に回せば、住宅ローンに縛られるより効率的に資産形成を行える可能性もあります。特に将来の不確実性を考えると、賃貸の方が経済的リスクをコントロールしやすいといえるでしょう。
移動のしやすさ
現代は転勤や転職、副業やリモートワークといった働き方の多様化が進み、住む場所を固定することのリスクが高まっています。マイホームを所有すると、転居時には売却や賃貸化といった手間とコストが発生します。郊外や地方の物件では、流動性の低さから買い手や借り手が見つからず「動けない」状況に陥る可能性もあります。
一方、賃貸は契約更新や解約によって比較的容易に住み替えができます。子育て期には広めの賃貸、子どもが独立した後にはコンパクトな住まい、といった柔軟な対応が可能です。ライフイベントや経済状況に応じて「最適な住まい」を選び直せる点は、持ち家にはない大きな魅力です。
新築プレミアム
日本の住宅市場には「新築プレミアム」という特有の現象があります。新築物件は割高に販売される一方で、購入直後から資産価値が目減りする傾向があります。マンションを新築で購入した場合、数年後には購入価格の7割程度まで下落することが珍しくありません。
この現象は住宅を「資産」と捉える際に大きなリスクとなります。対して賃貸は、新築プレミアムによる損失を居住者が直接負う必要がなく、利用料としての家賃を支払うだけで済みます。築浅物件を選んで快適な生活を送りつつ、資産価値下落のリスクを回避できるのは賃貸ならではのメリットです。
日本の人口減少と住宅需要
日本はすでに人口減少社会に突入しています。総務省の統計によれば、総人口は減少を続け、特に地方や郊外では空き家が急増しています。2030年には全国の住宅の3軒に1軒が空き家になるとの予測もあります。
こうした状況では、住宅を所有しても将来的に買い手がつかない、あるいは資産価値がほとんどなくなるリスクが高まります。都市部の一部人気エリアでは価格が上昇していますが、人口全体が減少する中でこの傾向が長期的に続く保証はありません。むしろ過剰供給の影響で、住宅価格は下落傾向に向かう可能性が高いといえます。
賃貸であれば、こうした資産価値下落のリスクを直接負担せずに済みます。人口減少で需要が落ち込めば、家賃も下がり居住コストを抑えられる可能性すらあります。
地方と都市の違い
住宅選びを考える際には、地方と都市で事情が大きく異なる点を理解する必要があります。
**都市部(東京・大阪・名古屋など)**では、人口の流入が続き、賃貸需要が高いため住宅価格や家賃は相対的に高止まりしています。持ち家を購入すれば値下がりリスクは地方より低いですが、それでも新築プレミアムや将来の金利上昇リスクは避けられません。むしろ価格が高い分、ローン負担や固定資産税も重くなり、失敗した場合のダメージも大きくなります。賃貸であれば高額な初期費用をかけずに都市の利便性を享受でき、転勤や転職などで柔軟に動ける点は大きな強みです。
一方、地方では住宅価格が都市部に比べて格段に安く、一戸建てを手に入れやすいという魅力があります。しかし、地方では人口減少と高齢化が急速に進んでおり、今後さらに空き家が増えることが確実視されています。購入した住宅の資産価値がほぼゼロ、場合によっては解体費用がかかる「負動産」と化すリスクもあります。さらに公共交通機関が乏しい地域では、自動車依存が強まり、生活コスト全体が上昇する傾向もあります。
このように、都市部は価格が高すぎ、地方は資産価値維持が困難というジレンマを抱えています。どちらにおいても「持ち家の経済合理性」は薄れつつあり、賃貸の方が柔軟性とリスク管理の点で有利だといえるのです。
文化的・心理的観点
「家を持ってこそ一人前」という文化的価値観は、戦後の高度経済成長期に形成されたものでした。土地神話や年功序列の雇用慣行とセットで機能していた時代には合理性がありましたが、人口減少と雇用流動化が進む現代では必ずしも通用しません。
老後の住まいに関しても、賃貸は不安だと言われがちですが、実際には高齢者向け賃貸やサービス付き高齢者住宅が増加しており、持ち家で老朽化した家に住み続けるよりも利便性や安全性が高い場合が少なくありません。
以上の観点を整理すると、マイホームには確かに「資産として残る」「住宅ローン完済後は住居費が減る」といった利点があります。しかしその裏には、ローン返済の重荷、金利リスク、固定資産税や修繕費、新築プレミアムによる資産価値下落、人口減少による需要縮小、地方の空き家リスクといった課題が存在します。
一方、賃貸には「家賃が一生続く」というデメリットがあるものの、経済的な柔軟性、移動のしやすさ、資産価値下落リスクの回避、ライフイベントに応じた選択の自由度など、多くのメリットがあります。都市と地方の双方におけるリスクを総合的に考慮すれば、今後の日本社会においては「賃貸の方が合理的である」というのが私の考えです。
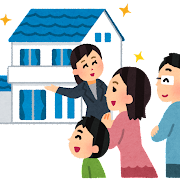


コメント